0-3.瞑想の学び方
※本ブログはseesaaブログで公開してきたものに修正をかけたものです
0.プレクシャ瞑想教室のねらい
| 0-3.瞑想の学び方 |
瞑想は実践練習してなんぼです。いくら哲学や理論・テクニック、先人の言っていることを頭に入れても、それはひとつも理解してわかったことにはなりません。
また、哲学やテクニックの細部にこだわりすぎるのも問題です。それは、瞑想の目的地を見失いかねないですし、実践がおろそかになりがちだからです。
瞑想の目的は生きとし生けるものが真の幸福と平和へたどり着くことであり、永遠不滅の清らかな魂を各自が取り戻すためです。
この目的地へのプロセスにおいて、実践・哲学・テクニックと生き方が有機的につながっていくのが本来的ですから、以下のことを常に念頭に置いて取り組んでください。
※学び方には人それぞれタイプがあります。理論や理屈をしっかりと理解するほうが実践がはかどる人はそのほうがいいに決まっています。ともかく、実践が必ず伴わなければ無意味だということは強調させてください。
| 1.常に実践を出発点とする |
理論・理屈を優先するのではなく(重要ではないと言っているのではありません)、取り組んでみて得たことや理解できたことを積み重ねることによって、理論・理屈はあとからついてきます(=理解できてきたり理論や理屈を深めたくなっていくということです)。また、どの分野にもあることですが、理屈や理論では解りえないこともあります。「ちょっと腑に落ちないけれど、とにかくそういうことなのかぁ。とりあえずやってみよう!」というのが、意外と重要です。瞑想は実践の哲学であり実践の幸福実現法ということを了解して取り組んでください。ただし、出発前に目的地をしっかりと了解しておいてください。
| 2.感覚を感じ、観じること |
瞑想の源流は知覚、すなわち感じ・観じることです。心身の内外で起こっている、あるいは起こってくる感覚に意識を集中させて、魂の声なき声である感覚をよく観察します。各種テクニックはこの知覚のための手段です。
| 3.原因と結果の関係を考えること |
取り組んで知覚して得たものの背後には、自分の生き方や人生上での様々なトラブル、はたまた嬉しいことや良いこと、わかっちゃいるけどやめられないことといった繰り返される現象、また自分の身の周りや社会で起こっている様々な出来事といったことなどを生み出している原因が潜んでいます。そこには『原因と結果の法則』が働いていて、この『原因と結果の法則』について理解を深めるために、哲学や先人たちの知恵を拝借し、自分自身の経験や感覚の観察を基礎に理解や哲学を深め構築していってください。この『原因と結果の法則』の理解を深めることが、『自分が自分の医者になる』ということです。
| 4.感じ・観じたこと、理解した原因と結果の法則との関連を理解し、日常へ活かすこと |
瞑想を通じて学び得たことは、日常へ活かしてこそ意味があります。『日常へ活かしてはじめて瞑想をした』といっても過言ではありません。なぜ瞑想をするのかというと、それは前述したように生きとし生けるものの幸福と平和を実現するためです。争いやトラブルを生み出しているのは、原因と結果の法則に気づかず同じ過ちを繰り返しているからです。瞑想の学びを少しずつ日常で応用して実践していきましょう
ふくヨガ~自分が自分の医者になる冥想ヨガ~ 文京区・池袋・厚木・茅ヶ崎・秦野・御殿場・Zoom
https://www.fukuyogamedita.com/
SNS
Facebook pageFacebookTwitterInstagramYouTube(メイン:プレクシャ瞑想の解説などが中心)Youtube(サブ:ヨガや瞑想を絡めた雑談などが中心)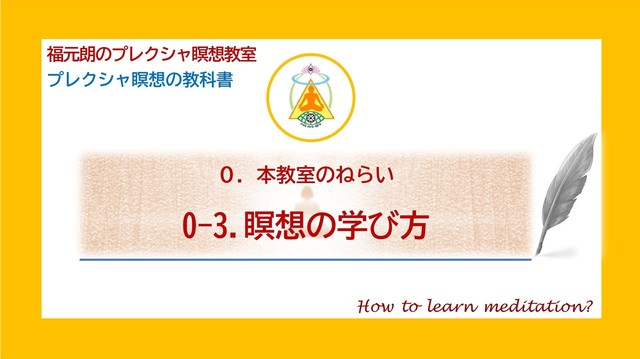

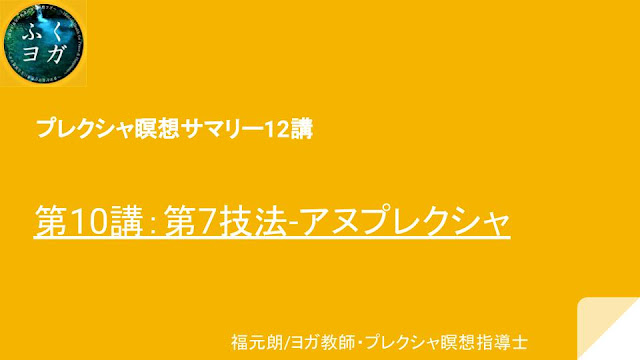

コメント
コメントを投稿